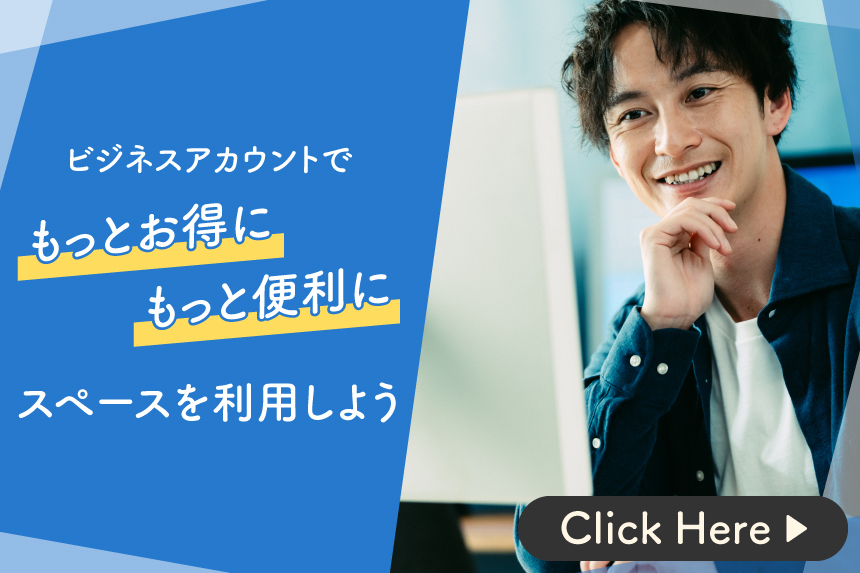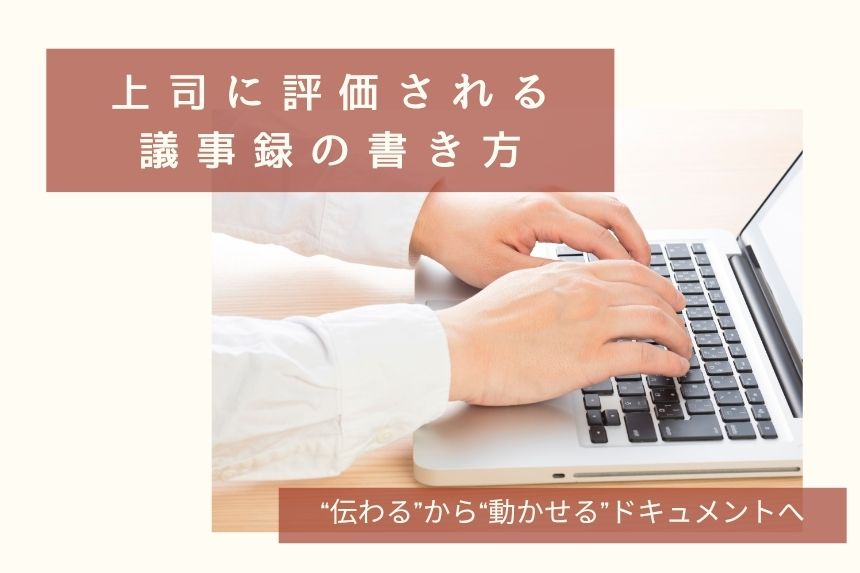
上司に評価される議事録の書き方|“伝わる”から“動かせる”ドキュメントへ
議事録を提出したものの、
「結局何が決まったかよくわからない」
「要点が伝わってこない」
そんなフィードバックをもらったことはありませんか?
ただ記録するだけでは、会議の“意味”は社内に伝わりません。
この記事では、読み手の行動を促す“評価される議事録”の作成術を紹介します。
社内での信頼や評価を高めたい方は、ぜひ参考にしてください。
議事録は“読む人のための資料”である
書く目的を「上司」や「関係者」に設定しよう
議事録は「自分の記録」ではなく、「他人に見せるための文章」です。
読む人にとって、以下のような情報が明確であることが重要です。
・何が話し合われたか
・どこまで決まったか
・次に誰が何をするのか
つまり、読むだけで“次の行動”がわかることが優れた議事録の条件です。
評価される議事録に共通する5つの特徴
1. 冒頭に“会議の目的”が簡潔に書かれている
議題が多い場合でも、1~2行で「この会議の意図・ゴール」が書かれていると、読み手の理解度が一気に上がります。 例: 本会議は、来期予算案の最終確認と営業部の体制変更についての決定を目的とする。
2. 決定事項が明確に記載されている
読み手が一番見たいのは「何が決まったか」。
本文内に埋もれず、見出しや箇条書きで分かりやすく記載しましょう。
悪い例:
「新商品の方向性について複数の意見が出た」
良い例:
【決定事項】新商品Aは、9月発売を目標とする。開発責任は〇〇氏。初回ロットは3,000個。
3. 担当者と期限がセットになっている
「誰が、いつまでに、何をするか」が明確でない議事録は、読み手に負担をかけます。
タスクは“アクション+担当+期日”で記録しましょう。
例:
・資料ドラフト作成:営業部△△さん(〜6/30まで)
・会場手配:総務課□□さん(〜7/5)
4. 話し合いの過程も簡潔に残す
決定に至るまでの背景や対立意見も、要点だけ残しておくと後の検証やトラブル回避に役立ちます。
ただし、長々と書かず、あくまで要約でOK。
例:
現行案に対して、コスト増を懸念する声あり。対案として別工場での生産提案があったが、納期の観点から却下。
5. 読みやすさが意識されている
・見出し(【決定事項】【意見】【対応方針】など)を活用
・余白を適度に取り、ブロックごとに分ける
・長文は避け、短い文でまとめる
“伝わる議事録”は、読みやすいレイアウトから生まれます。
議事録作成をラクにする工夫
テンプレートを自分用にカスタマイズする
毎回ゼロから書くのではなく、自分の業務に合ったテンプレートを作成しておくと効率アップ&質の安定につながります。
項目例:
・会議名/日時/出席者
・目的
・議題1:内容/決定事項/アクション
・議題2:内容/決定事項/アクション
・次回開催日程
会議終了後、即メモを整理する習慣を
記憶が薄れる前に、一気にまとめておくのがベストです。
録音はあくまで補助。リアルタイムメモ+即整理が高品質への近道です。
よくあるNG議事録とその改善例
NG:主語が曖昧
✕「予算について検討することになった」
◯「経営会議にて、来期予算案を〇〇部長が再提案することが決定」
NG:行動に繋がらない曖昧な表現
✕「〜について引き続き対応」
◯「〜について〇〇が6月中に対応完了予定」
読み手が“どう行動すればいいか”が見えない表現は避けましょう。
まとめ|議事録は“あなたの評価”につながる武器になる
議事録は「書類作成」の枠を超えて、
あなたの理解力・要約力・伝達力がすべて表れるアウトプットです。
読み手の立場を意識して、構成と表現を一工夫すれば、
「わかりやすい!」「次もお願いしたい」と信頼を勝ち取ることができます。
明日から、“行動につながる議事録”を目指してみましょう。